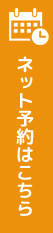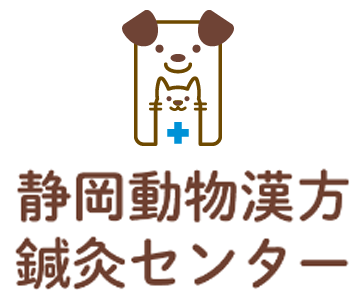⭐️消化器病の漢方治療について
✳️消化器病の漢方治療
病歴の長さ・種類・患者様の状態により使用する漢方生薬の組み合わせは異なります。
具体的な症状や病名に照らし合わせて、ご紹介いたします。
嘔吐→制吐漢方
下痢→下痢止め漢方
食欲不振→食欲増進漢方
膵炎→膵炎専用漢方
蛋白喪失性腸症に伴う低アルブミン血症→蛋白吸収促進漢方
不定期な下血→消化器止血漢方
これ以外にも消化器漢方はいくつもありますが、これらを単独で使用することもありますし、複数で使用することもあります。
📕解説
消化器の問題を考える場合、中医学では、1つの症状である『湿熱症』について考える必要があります。
✴️湿熱症
『湿』は、消化管に障害を引き起こします。
『湿』とは、わかりやすくいうと「体内の湿気』です。これが生じる原因は、
✨1.食べ物
🌟2.季節
があります。
順番にご説明いたします。
✨1.食べ物について
もともと消化機能が低いヒトや動物は、中医学では、『脾気虚(ヒキキョ)』という体質です。
✴️脾気虚の患者様の消化器症状としては、『お腹が弱く』以下のような症状が見られます。
・食欲ムラがあり、いつもいろんなフードを試してみるけど食べてくれない。
・不定期な嘔吐・下痢がある。
・いつも便がゆるい。
・体の線が細い
・太らない
・痩せている
・膵炎を再発する
などがあります。
*『脾(ヒ)』とは、消化器のことを指します。
食べ物の流れ
口→食道→胃の中へ
・本来、消化管と言うものは、滝を流れる水のようにサーッと内容物が通過するもの。
・消化機能が低い脾気虚の動物は、消化に時間がかかり、飲食物が胃の中に長くとどまる。
飲食物が胃の中に長く留まり、体温で温められる(炊飯器の中で、ずっとお粥を保温にしてるような状況)
炊飯器でお粥を5日間ほど保温状態にしていれば、発酵してきてドロドロになり腐ります。また発酵したときに『熱』を生じます。
この白米が、発酵して、ドロドロになったものが『湿』+その時に生じた『熱』とがあわさり、湿+熱=『湿熱』となる。
この湿熱が身体にいろいろな影響を及ぼし、その症状は、『湿熱症』となる。
『湿熱症』は様々な臓器に影響を及ぼす。
また、『湿』が『熱』でさらに蒸らされると、『痰』に変わる。
この『痰』と『湿』が合わさると、痰+湿=『痰湿』となる。
『痰湿』は、ネバネバとしたもの。
余分な湿や、生じた痰は、弱った臓器に影響します。
弱った臓器によって、以下に記載したような現象や症状が起きます。
・肺→喉に痰が絡む・ネバネバの鼻水
・肝臓→目から涙がたくさん出る・目やにがベタベタする・首から上の症状、眩暈など
・心臓→湿った咳が出る・胸の痛みなど
・腎臓→湿が多い→下半身に水が多い→下半身の冷え
・消化器→湿多い→食欲不振・嘔吐・下痢など
・皮膚→湿疹
🌟2.季節について
・『湿気』の多い季節、中医学上で、『長夏(チョウカ)』と言われる、現在の暦で7月を指す時期が最も消化器に影響を及ぼす。
・うなぎを食べる土用の丑の日近辺は、食中毒や下痢のご相談など、消化器症状がヒトでも多い。
・動物の場合、特に、ワンちゃん🐶で、飼い主様から『夏に食欲が落ちた』などのご相談を受けることが多く、7月だけではなく、現実的には湿気が増える3月〜10月くらいまでにご相談が多い。
また、漢方治療の臨床現場では、病気が複雑になったら、まず消化器から治療するという原則があります。
高度な治療テクニックですが、一見、消化器とは関係がない様な病気も、そのような方法で治療します。